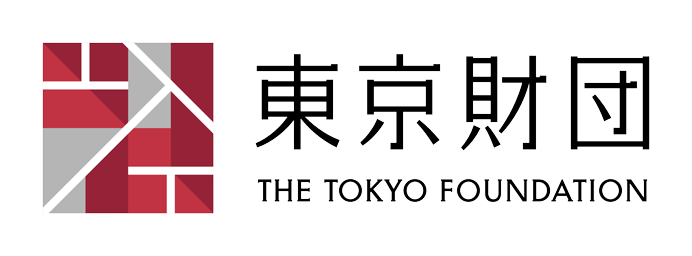国際シンポジウム 日本とユダヤ人 ―過去・現在・未来を見据えて―
日時:
会場:笹川平和財団ビル11階国際会議場
(東京都港区虎ノ門1-15-16)
目的および背景
戦後80年を迎えて、米中対立やウクライナ戦争の長期化など、世界は不確実性を増すとともに、「人道とは何か?」あるいは「公平とは何か?」を強く問われていると言えます。私たち東京財団は我が国が抱える人口減少問題を解決する方策を提案すべく、長期的な視野と自由な発想を持って調査研究を展開しています。そして、このような取り組みを進める上で、今後求められる取り組みについて議論するだけではなく、過去のさまざまな取り組みや事象を振り返ることも重要であると考えています。このような問題意識のもと、国際交流および国際協力の推進を目指し、国内外で新しいガバナンスのあり方を追求する活動、提言、交流等を展開している公益財団法人笹川平和財団の協力を得て、国際シンポジウムを開催する運びとなりました。
今回の国際シンポジウムでは、20世紀に急速に関係を深めた我が国とユダヤ人の関係性に焦点を当て、国家として、そして、人間として、あるべき姿を追い求めてきたそのユニークな関係性を振り返るとともに、これまでに我々が十分に認識することができなかったその実像を明らかにすべく、世界各国で活動する有識者や実務家の皆様をお招きします。
日本やユダヤ人の歴史のみならず、国際交流や国際協力のあり方に興味・関心のある皆様に是非ご出席いただき、新たな視点からも議論にご参加いただけますと幸いです。
- 日時
- 会場
- 笹川平和財団ビル11階国際会議場(東京都港区虎ノ門1-15-16)
- 言語
- 日本語・英語(同時通訳あり)
プログラム
登壇者紹介

中林 美恵子
大阪大学大学院国際公共政策研究科博士後期課程修了、博士(国際公共政策)。米国ワシントン州立大学大学院政治学部修士課程修了、修士(政治学)。1992年米国永住権取得後、連邦議会上院予算委員会に正規採用され約10年間勤務。在米14年を経て2002年に帰国。大学の教職や政府の各種審議会委員、衆議院議員(2009年~2012年)などを経て、現職。早稲田大学教授を兼ねる。著書に『アメリカの今を知れば、日本と世界が見える: 混迷が告げる時代大転換の予兆』東京書籍(2025)など多数。

ラビ・アンドリュー・シアー
ニューヨーク生まれ。ニューヨーク大学でユダヤ史の学士号を取得。大学卒業から神学校入学までの間、日本の地方で英語教師を務め、在日ユダヤコミュニティでヘブライ語学校の教師も務めた。イェシバット・ホヴェヴェイ・トーラー・ラビ養成学校在学中はウェクスナー・グラデュエート・フェローに選出。また、アメリカ陸軍予備役として5年間勤務し、その間ウェストポイントの陸軍士官学校に配属された。
ラビ叙任後は、ライカーズ島でニューヨーク市矯正局のユダヤ教チャプレンとして、またVAニューヨーク・ハーバー・ヘルスケア・システムで勤務した。

メロン・メッツィーニ
1932年、エルサレム生まれ。ヘブライ大学アジア学部名誉教授。ロシア革命後にソ連から逃れ、ハルビンで新聞記者、政治評論家だった父親の薫陶を受けてアジア研究のため米国留学、ニューヨーク市立大学で学士号取得。ジョージタウン大学で修士号を取得後、ハーバード大学でエドウィン・O・ライシャワー教授(のちの米国駐日大使)に師事、博士号取得。1962年から1978年まで帰国後イスラエル首相府報道局長を務め、レヴィ・エシュコル、ゴルダ・メイア、イツハク・ラビン首相のスポークスマンを歴任しつつ、ヘブライ大学で日本学講座を初めて持ち、イスラエルにおける日本研究の開祖。1973年からヘブライ大学で教授として日本近代史とイスラエル外交政策を教える。弟子にはベン=アミ・シロニー(日本学の大家)、エフード・オルメルト(のちのイスラエル首相)がいる。2016年に日本政府から旭日中綬賞を受賞。『ゴルダ―Aの政治伝記』(2010)はイスラエル首相賞を受賞。翻訳書として『日章旗のもとでユダヤ人はいかに生き延びたか ユダヤ人から見た日本のユダヤ政策』(勉誠出版)、『ユダヤ人と日本人』(WAC出版)がある。

石田 訓夫
1972年外務省入省、外務省ヘブライ語研修生としてエルサレム・ヘブライ大学留学。三度の在イスラエル日本大使館勤務とその他の海外勤務を経験。外務省中東地域調整官、政策企画官等を歴任。元外務省外交史料館長。
元南山大学客員教授、元早稲田大学非常勤講師、元同志社大学一神教学際研究センター共同研究員。講演:2002年ヘブライ大学トルーマン平和研究所主催日本・イスラエル国交樹立50周年記念シンポジウム、2010年トルーマン平和研究所主催シンポジウム。論文:「日本とユダヤ国家をめぐる20世紀の国際関係」『21世紀の国際関係』南窓社、南山大学紀要『アカデミア』社会科学編第3号、『外交史料館報』第26号その他。ヘブライ大学より2002年修士号、2010年博士号を授与される。
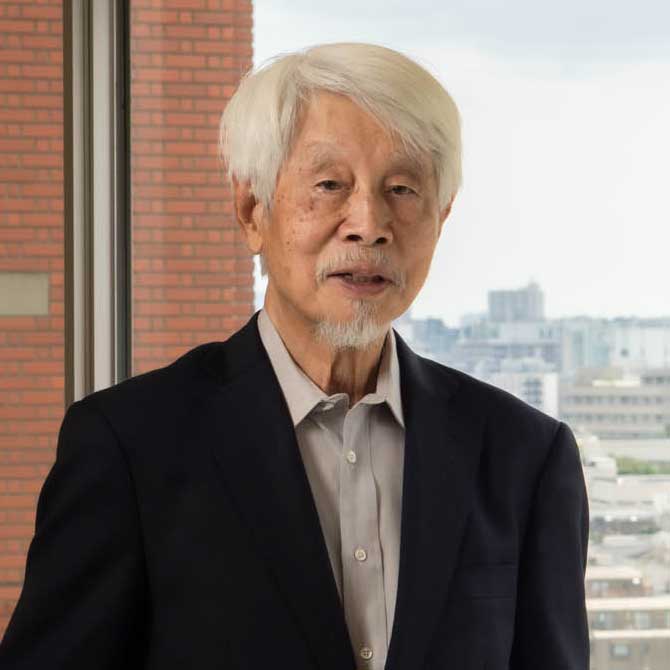
丸山 直起
1942年長野県生まれ。1975年に小樽商科大学助教授に就任。1983年より国際大学大学院教授、1991年より明治学院大学法学部教授を歴任し、2010年、同大学名誉教授となる。法学博士(一橋大学)。
専門はアメリカのユダヤ人社会、太平洋戦争期のユダヤ難民、ホロコーストとアメリカの難民政策であり、これらの分野で数多くの業績を残している。主な著書に『アメリカのユダヤ人社会:ユダヤ・パワーの実像と反ユダヤ主義』(ジャパンタイムズ、1990年)、『太平洋戦争と上海のユダヤ難民』(法政大学出版局、2005年)、『ホロコーストとアメリカ:ユダヤ人組織の支援活動と政府の難民政策』(みすず書房、2018年)がある。また、英文論文も多数発表し、国際的な視点からユダヤ人問題および日本の外交政策に関する研究を行っている。

ニシム・オトマズキン
国立ヘブライ大学教授。トルーマン研究所所長を経て、同大学人文学部長。1996年、東洋言語学院(東京都)にて言語文化学を学ぶ。2000年ヘブライ大学にて政治学および東アジア地域学を修了。2007年、京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科修了、博士号を取得。同年10月、アジア地域の社会文化に関する優秀な論文に贈られる第6回井植記念「アジア太平洋研究賞」を受賞。2012年、エルサレム・ヘブライ大学学長賞を受賞。研究分野は「日本政治と外交関係」「アジアにおける日本の文化外交」など。京都をこよなく愛している。

新居 雄介
1967年東京都生まれ。1990年3月に東京大学経済学部を卒業後、同年4月、外務省に入省。北米局日米安全保障条約課企画官を務めた。その後、在大韓民国日本国大使館参事官、在シンガポール日本国大使館公使として在外勤務を経験。本省では、大臣官房広報文化外交戦略課長、総合外交政策局安全保障政策課長を歴任し、日本の外交政策の策定に深く関与。
特に、国際情報分野において重要な役職を担い、2022年9月には国際情報統括官に就任。2024年4月からは特命全権大使としてイスラエル国に駐箚しており、国際社会における日本の外交を牽引している。

岡部 伸
1959年生まれ。81年、立教大学を卒業後、産経新聞社に入社。米デューク大学、コロンビア大学東アジア研究所に留学。米グランド・フォークス・ヘラルド紙客員記者。モスクワ支局長、ロンドン支局長を経て論説委員。客員論説委員、東京財団シニアアドバイザー、麗澤大学客員教授。『消えたヤルタ密約緊急電─情報士官・小野寺信の孤独な戦い』(新潮社)で第22回山本七平賞受賞、『「諜報の神様」と呼ばれた男』『イギリスの失敗「合意なき離脱」のリスク』『第二次大戦、諜報戦秘史』(いずれもPHP研究所)、『新・日英同盟─100年後の武士道と騎士道』(白秋社)、『至誠の日本インテリジェンス』(ワニブックス)などの著書がある。

笹川 陽平
アジア最大級の民間財団・日本財団の名誉会長として、アジア、アフリカ、南米など世界各地で社会課題の解決に尽力している。徹底した現場主義に基づく草の根の活動を重視しつつ、国際的リーダーとの広範なネットワークを生かして具体的成果を追求する姿勢を貫く。年間100日以上を海外活動に充て、半世紀にわたりハンセン病の制圧と差別撤廃に取り組むほか、アフリカにおける農業支援、日本政府代表としてミャンマーにおける国民和解の仲介、奨学金事業を通じた人材育成、障害者支援、海洋の専門家の養成を通じた海洋課題解決など幅広い取り組みに従事している。イスラエルにおいても1980年代から民間の立場から両国の関係強化に尽力し、ティコティン・ミュージアムの建設やベングリオン大学での奨学金事業を支援するほか、本年は4月にイスラエルを訪問しヘルツォグ大統領ら要人らと会談を行った。

水内 龍太
1959年、東京都出身。83年、外務省入省。国際情報局分析第一課長、内閣官房内閣衛星情報センター分析部長、在デュッセルドルフ総領事、駐ザンビア、駐オーストリア大使などを歴任。イスラエル在勤中(2004~07)にテディ・カウフマン氏(ハルビン・ユダヤ人社会指導者アブラハム・カウフマン博士の子息)、ウィーンから「樋口ルート」で脱出したユダヤ人の子息などと交遊。杉原千畝や樋口季一郎に関する研究をヘブライ大学やウィーン大学で発表。
現在、日墺協会評議員、日墺文化協会理事。

樋口 隆一
明治学院大学名誉教授。1946年4月東京生まれ。慶應義塾大学文学部卒、同大学院博士課程中退。西ドイツに国費留学し、テュービンゲン大学哲学博士(音楽学)。「新バッハ全集」校訂者、シュトゥットガルト聖母マリア教会代理合唱長。帰国後は音楽学者、指揮者として活躍。2012~17年、国際音楽学会副会長。京都音楽賞研究評論部門賞、辻荘一生賞、テオドル・ベルヒェム賞(ドイツ)、オーストリア学術芸術功労十字章。明治学院バッハ・アカデミー芸術監督・指揮者。日本アルバン・ベルク協会会長、音楽三田会会長、一般財団法人樋口季一郎顕彰会代表理事。『バッハ』、『バッハ・カンタータ研究』等、著訳書多数。バッハ『マタイ受難曲』、モーツァルト『レクイエム』等、CD多数。『陸軍中将樋口季一郎の遺訓』など、祖父の遺稿の出版に尽力。

ロバート・D・エルドリッヂ
政治学博士、日本国際問題研究所・シニアフェロー、エルドリッヂ研究所・代表。1968年、米国に生まれる。パリ留学を経て、米リンチバーグ大学の国際関係学部を優等卒してから90年来日。兵庫県多可町町立中学校の初ALT。99年、神戸大学法学研究科博士課程後期課程終了(五百旗頭眞教授の指導のもとで)。サントリー文化財団研究員、大阪大学准教授、在日海兵隊基地外交政策部次長を経て現職。専門分野は日本政治・外交史、安全保障、危機管理、防災、地方創生、国際交流、教育。『沖縄問題の起源』、『尖閣問題の起源』、『オキナワ論』、『次の大震災に備えるために』、『トモダチ作戦』、『人口減少と自衛隊』、『教育不況からの脱出』等多数。樋口季一郎中将顕彰会・理事、日台国際桜交流会・理事、北海道大学新渡戸カレッジ、沖縄国際大学、法政大学など客員研究員、グローバルリスクミティゲーション財団理事(北東アジア担当)。Japan Times、 Japan Forward、現代ビジネスなどのコラムニスト、テレビ、ラジオ出演など活躍中。詳細はこちらをご参照。

白石 仁章
1963年生まれ。1987年上智大学卒業、同大学院に進み、1989年修士号を授けられる。1994年上智大学大学院博士後期課程単位取得満期退学。1989年外務省外交史料館に外務事務官として採用され現在に至る。当初は戦間期における日ソ関係をテーマに研究していたが、1990年に杉原千畝令夫人故幸子氏『六千人の命のビザ』に出会い、大変感銘を受け、それ以来杉原千畝関係を研究テーマとして現在に至る。主著に『諜報の天才 杉原千畝』(新潮社)と同書の増補・改訂版である『杉原千畝 情報に賭けた外交官』(新潮文庫)がある。

パメラ・ロトナー・サカモト
1962年にノースカロライナ州に生まれる。アマースト大学卒業。1984年に「アーモスト・同志社フェロー」として来日。以降、京都と東京で通算17年間を過ごす。タフツ大学フレッチャー法律外交大学院でPh.D.を取得。長年にわたり米国ホロコースト記念博物館における日本関係のプロジェクトで専門コンサルタントを務めている。2007年にハワイに移住。ハワイ大学と名門私立校プナホウ・スクールで歴史を教える。最新の翻訳書として『黒い雨に撃たれて、上下』(慶應義塾大学出版会、2020年)がある。
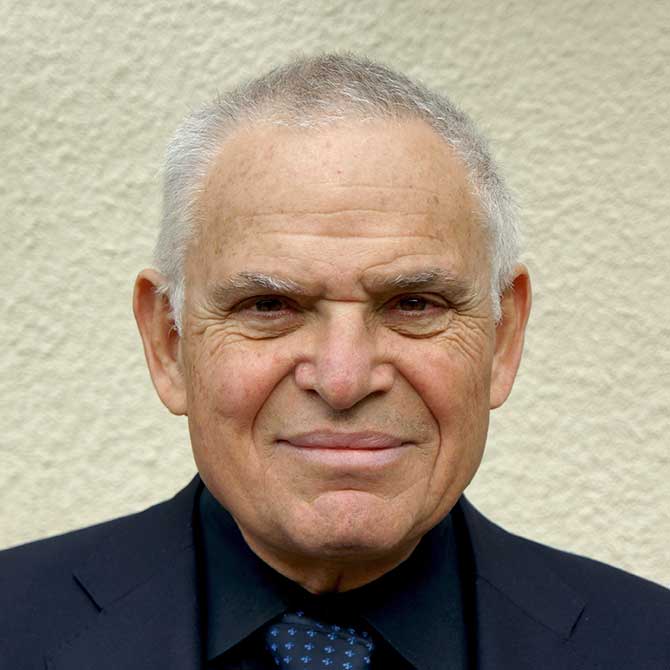
エドワード・N・ルトワック
1942年ルーマニアのトランシルヴァニア地方アラド生まれの戦略家、歴史家。パレルモ、カーメル・カレッジで学び、ロンドン大学(ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス)で学士号(1964年)を取得。1967年から72年までイスラエルで戦略アナリストとして活動後、ジョンズ・ホプキンズ大学で博士号(1975年、『ローマ帝国のグランド・ストラテジー』)を取得。1977年には米国議会法により米国市民権を得ている。
現在、米国政府の戦略アドバイザーを務める。これまでに米国大統領政権移行チームに参画し、米下院・上院の委員会で証言。米国防総省、陸軍、海軍、空軍、ホワイトハウス首席補佐官、二つの欧州政府、そして日本政府のコンサルタントを歴任した。著書に『エドワード・ルトワックの戦略論』『中国の戦略』『戦略:戦争と平和の論理』(いずれもハーバード大学出版局)など27言語で出版された10冊がある。軍事戦略、地政学、外交に関する深い洞察は、世界中の政策立案者や研究者に影響を与えている。

角南 篤
公益財団法人笹川平和財団理事長、昭和音楽大学学長、デロイトトーマツ戦略研究所代表理事、政策研究大学院大学学長特命補佐・客員教授、早稲田大学ナノ・ライフ創新研究機構客員教授。専門は国際関係論、公共政策論(科学技術・イノベーション政策)。内閣府参与を経て、内閣府沖縄振興審議会会長、文部科学省日本ユネスコ国内委員会副会長、内閣官房経済安全保障法制に関する有識者会議委員、内閣府総合科学技術・イノベーション会議専門調査会委員等を務める。その他、国連海洋科学の10年国内委員会共同座長、NIKKEIブルーオーシャン・フォーラム有識者委員会共同座長、JAXA宇宙戦略基金プログラムオフィサー、JAXA衛星地球観測コンソーシアム会長、月面産業ビジョン協議会共同座長等を務める。コロンビア大学政治学博士(Ph.D.)、コロンビア大学国際関係・行政大学院国際関係学修士(MIA)、ジョージタウン大学外交学学士(BSFS)。
本件に関するお問い合わせ
東京財団・笹川平和財団共催国際シンポジウム事務局
電話:03-5244-5364(平日10時から18時)